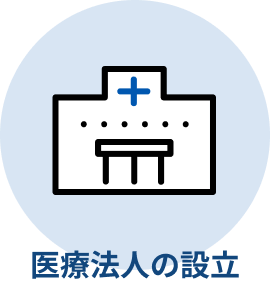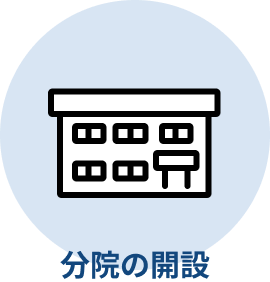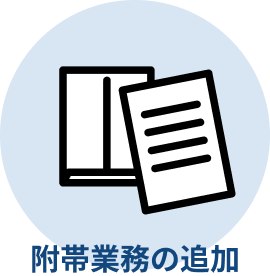行政ごとに変わる細かな申請ルールに対応できます!
医療行政手続きには、行政・役所ごとに異なる細かな申請ルールが存在します。当社のサービスでは、これらのルールに迅速かつ正確に対応し、申請を全て引き受けます。複雑な手続きも安心してお任せください。スムーズな申請をサポートし、業務効率を 大幅に向上させます。
行政手続きの例
医療関連の行政手続きには地域ごとに異なったルールが存在します。行政手続きの例としては、個人診療所の開設、医療法人の設立、診療所の移転、分院の開設、附帯業務の追加、非営利型の一般社団法人の設立、理事・監事の変更手続き(役員の変更)、など多岐にわたります。
行政手続き失敗事例
同じ医療法人の申請で片方は即日受理、もう片方は差し戻し
あるクリニックの先生が、2つの都道府県で分院を展開しており、それぞれの所在地で医療法人関連の手続きを行うことになりました。片方の地域では役員変更の届出がすんなり通ったのに、同じ書類を使って提出したもう一方の地域では「添付書類が不足しています」と差し戻しに。その地域では就任承諾書・印鑑証明書・議事録の写しまで求められていたのです。
また別の事例では、介護事業を始めたいというクリニックが「附帯業務の追加申請」をしたところ、ある自治体では事業計画書だけで受理された一方、他の自治体では損益予測と市町村の同意書の添付が求められ、想定より1か月以上手続きが遅延しました。いずれも、医療法上は全国共通の制度でありながら、「運用上の差」で現場の負担が大きく異なることを示しています。
都道府県によっては書類だけでなく、解釈と対応にもズレがあります。手続きの差は、単なる「書類の種類」だけにとどまりません。
定款変更時、ある自治体では「理事会の議事録」で十分でも、別の地域では「社員総会の議事録」も求められる
開設許可において、床面積に関する基準が自治体によって微妙に異なる
法人名の付け方や、附帯業務の表現が“厳密に制限”される自治体もある
さらに担当者によって対応が異なることもあり、「以前は通ったのに今回は却下された」といったケースすらあります。これは申請者本人がルールの最新運用まで把握していない限り、避けられないトラブルです。

医療法人手続きの見えないストレスとは?
書類のやり取り、行政からの電話、差し戻し…日々の診療やスタッフマネジメントに加えて、慣れない役所対応まで抱えるのは、医師や事務長にとって極めて大きな負担です。地域差による申請の遅延やミスは、以下のような影響を及ぼします。
事業開始のスケジュールが後ろ倒しになる
人事異動が予定通りに進まない
役員の法的任期に間に合わず、無資格状態とされるリスク
だからこそ、地域に合った事前準備が申請には不可欠なのです。
私たちの強み
――全国対応×現場主義で、地域ルールにも万全
総合経営サービスでは、全国150件超の医療法人設立、800件以上の医療手続き支援を行ってきた実績から、各地の行政の運用ルールに精通しています。単なる書類作成ではなく、申請が確実に通るためのサポートを徹底しています。
「役所の対応が不安…」
――そんな方こそご相談ください
制度や法律だけでなく、“実際に現場でどう動くか”を知っているからこそ、医療機関の皆さまから高い評価をいただいています。
-

こんなにスムーズなら、もっと早く頼めばよかった
-

自分では難しかった附帯業務の申請が通った
-

書類作成から提出まで全部任せられて安心だった
複雑な行政手続きも、まとめてお任せください。医療機関特有の行政手続きは、一見シンプルに見えても「地域ごとの落とし穴」があります。だからこそ、専門家の支援が必要です。私たちは、単なる代行業者ではありません。地域のルールを読み解き、行政との橋渡しを行うパートナーとして、医療経営を支えます。「行政が違うから不安…」「書類がこれで合っているか分からない…」そんなお悩みがある方は、ぜひ一度ご相談ください。
手続きに関わる税務、労務、登記などの業務もサポート!
税務、労務、登記などの複雑な業務も一括してサポートします。当社の強みは、会計事務所として長年にわたり培ってきた専門知識です。その強みを活かしたワンストップのトータルサービスで、煩雑な手続きを全て請け負います。安心して診療などの本業に専念できる環境を提供します。
専門家がバラバラだと、経営者は本業に集中できない
――“同じ話を何度もしなければならない”という現場の悩み
クリニックの経営者の方々とお話をしていると、税理士、社労士、司法書士、行政書士などの専門家を別々に頼んでいるために、「同じ話を何度もしなければならない」といった声をよく耳にします。
経営者にとって本来最も大切なのは、「医療の質を高め、組織を良くし、地域の信頼を得る」こと。にもかかわらず、手続きや相談のたびに専門家を切り分け、何度も同じ説明を繰り返すことに時間と神経を取られてしまっては、本業への集中は難しくなってしまいます。
一見、専門家が複数いることは心強く見えるかもしれません。しかし同じ屋根の下で、気持ちを同じ方向に向けて動ける専門家が揃っているかどうかこそが、経営者にとって最大のパートナーとなり、事務的負担を最小限に抑えるポイントになるのです。

バラバラ対応によって起きたクリニック現場の
「よくある3つのトラブル」
事例①
役員変更で“3人の専門家”に別々に連絡
書類不備で差し戻し
ある医療法人では、理事長交代に伴う役員変更手続きを進めていました。税務は顧問税理士に、社会保険の変更は社労士に、登記は司法書士に依頼していましたが、全員に同じ内容を別々に説明する必要がありました。さらに、就任日について税理士は“月初”と認識していたのに対し、司法書士は“理事会開催日”として書類を作成。内容の不一致が原因で登記が差し戻され、再提出を余儀なくされました。結果、再度全員に連絡を取り直して理事長の予定も調整し直す必要が生じ、2週間以上のロスが発生しました。
事例②
診療報酬と人件費のデータが不整合
決算書類に修正発生
あるクリニックでは、スタッフの入退職に関する情報を社労士に伝えていたものの、税理士には伝わっておらず、賞与額の調整も未反映でした。結果、試算表に記載された人件費と、実際の支払額に差異が生じ、決算書の再作成が必要に。一部内容は税務申告にも影響し、最終的に修正申告に至りました。この一件で、事務長は約15時間の対応を強いられ、本来業務である診療運営が一時停滞することとなりました。
事例③
補助金申請で“要件の誤解”
申請却下
あるクリニックでは、IT導入補助金を活用して電子カルテシステムの導入を計画していました。申請書類の作成は行政書士に依頼し、システム選定はITベンダーと進めていましたが、補助金の対象となる経費範囲や要件についての理解が不十分でした。具体的には、補助金の対象外となるオプション機能を含めた見積もりを提出してしまい、審査段階で指摘を受けました。また、導入予定のシステムが補助金の登録ITツールに該当していないことが判明し、結果として申請が却下される事態となりました。このように、各専門家が連携せずに進めたことで、補助金の要件を正確に把握できず、申請のチャンスを逃す結果となってしまいました。
「専門家が揃っている」だけでは足りない
――求められるのは“経営者の右腕”となる体制
このように、税務・労務・登記・行政の実務は、互いに密接に関連しています。しかし、別々の事務所や担当者に依頼していると、
情報伝達のムダ
意思統一のズレ
時間のロス
といった「目に見えないコスト」が日々発生します。
クリニック経営において「医療に集中できる時間」は何よりも貴重です。そこを奪っている要因の一つが、「専門家同士の連携不足」による事務負担の増加なのです。
STAFF 担当スタッフ紹介

税理士法人総合経営サービス 代表社員、一般社団法人中小企業成長支援センター 代表理事、一般社団法人ライフデザイン協会 代表理事
石川県出身。 所内では法人顧客・個人顧客問わず決算・申告最終チェック者として、節税対策・税務調査対応、相続対策に従事。 現在は総合経営サービスグループの税理士法人・税務部門長職に就いている。各種セミナー講師も務める。 相続分野では、家族信託、身元保証、高齢者への住まい紹介なども対応している。 近年需要の多いバックオフィス改善(経理の効率化)についても経理周りのクラウド化、書類の電子化等を積極的に進めており、会計事務所の枠にとらわれないサービス提供を心掛けている。 人材育成にも力を入れており、所内研修の講師も数多く務めている。(累計1000回以上)

長崎市出身。演劇人になるために上京。その後、コールセンターでお客様対応業務から新人育成及び事務業務まで行なっていたが、カメラマン、事務職等も経験。コロナ禍で資格の重要性に気づき、一念発起。行政書士の資格をはじめ、簿記、FPの資格を取得。お客様に寄り添い、より良い提案ができる実務家でありたいと日々勉強しております。