2025年7月23日
はじめに
医療法人設立は、一般企業のようにスピーディに設立できるものではなく、医療法に基づく厳格な認可制度の下で進められます。特に、医師や歯科医師の方が個人で診療所を運営していた場合、法人化により社会的信用の向上や節税、事業承継の円滑化といったメリットがある一方で、構成員(社員)の選任、定款の作成、収支予算書の整備、役員選定など、多くの準備事項を一つずつクリアしなければなりません。また、都道府県ごとに異なる受付期間や審査基準が設けられているため、「全国一律の流れ」がある一方で「各地域特有の注意点」も存在します。医療法人の設立は単なる形式上の変更にとどまらず、今後の経営や診療体制に大きな影響を与えるため、最初の段階で全体像を把握することが何より重要です。この“全体像を掴む”という作業こそが、最短での法人設立と、その後のスムーズな事業運営につながります。
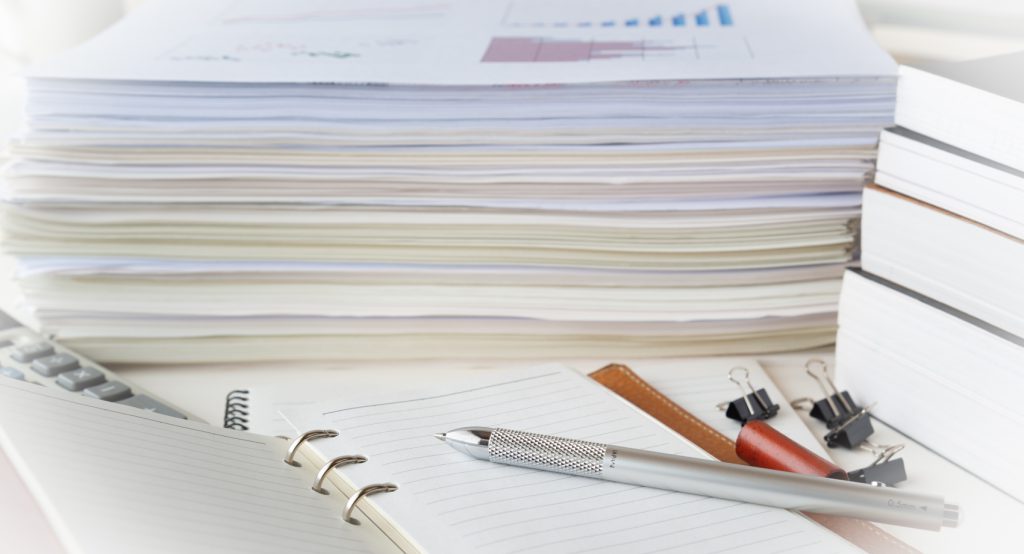
医療法人設立の全体スケジュール概要
医療法人設立のプロセスは一見複雑に見えるかもしれませんが、段階的に整理することで明確な道筋が見えてきます。大まかには、(1)準備段階、(2)仮申請(事前審査)、(3)本申請・審査・認可取得、(4)法人登記、(5)医療機関の開設許可・届出、(6)保険医療機関指定申請、(7)開設後の各種手続き、という7つのステップで構成されます。ここで注意したいのは「逆算思考」です。たとえば、希望する診療開始日から逆算し、いつまでに申請書を出すべきかを把握しなければ、仮申請や本申請の機会を逃してしまう可能性があります。東京都のように年2回の受付期間が明確に定められている自治体も多く、そのタイミングに間に合わせるには、申請の3〜4か月前からの着手が必須です。また、仮申請と本申請の間で書類の差し替えが基本的に認められていないため、準備段階での完成度が後の流れを左右します。このように、法人設立は「申請日ありき」ではなく「準備の質ありき」と言っても過言ではありません。
-
01準備段階(事前相談・計画策定)【約2〜3か月】
法人の骨組みをつくる段階。社員・役員の選定や事業計画を固めます。
-
02仮申請(事前審査)【約3〜4か月】
内容確認・不備指摘がされるステップ。実質的な審査がここで行われます。
-
03本申請・審査・認可取得【約2〜3か月】
公的な書類提出と正式な認可取得に進む段階。書類の完成度が問われます。
-
04法人設立登記【認可後2週間以内】
登記によって法人格が付与され、ようやく“法人”として成立します。
-
05医療機関の開設許可申請・届出
医療提供体制としてのハード面(設備・構造)の基準がチェックされます。
-
06保険医療機関指定申請
保険診療を行うにはここで「指定」を受ける必要があります。タイミングも重要。
-
07開設後の諸手続き(税務・社保・医師会など)
法人としての実務がスタート。届出漏れや社会保険の適用忘れに要注意です。
①準備段階(事前相談・計画策定)【約2〜3か月】
この準備段階が、医療法人設立における“要”とも言える部分です。ここで行う作業は、単なる事務手続きにとどまらず、今後の経営方針を形にしていく作業そのものです。定款や事業計画書、収支予算などの資料は、単に行政に提出するための書類ではなく、開業後の法人運営を想定したシミュレーションとして機能します。誰が理事になり、誰が社員として名を連ねるかといった「人の構成」もこの段階で決定されます。特に社員(出資を伴わない構成員)の人数は3名以上と法定されており、形だけでなく実質的に責任を持つ人材を選定する必要があります。また、診療所の場所や開設資金の根拠資料(見積書や預金残高証明書など)も準備が必要で、不動産取得や内装工事のスケジュールも視野に入れた動きが求められます。ここでの段取りが甘いと、以降のフェーズで何度も差し戻しや修正が必要になり、開業時期が大きくずれる原因になります。行政書士や税理士など、医療法人に強い専門家と伴走しながら進めることで、リスクを最小限に抑えることができます。
- 定款案(寄附行為案)
- 設立趣意書・事業計画書
- 収支予算書・財産目録
- 社員名簿・役員候補者リスト
- 設立総会議事録(案)
- 診療所または病院の施設概要、平面図、設備一覧
- 診療科目、医療スタッフの体制案
- 開設資金関連(見積書、預金残高証明書 など)
②仮申請(事前審査)【約3〜4か月】
仮申請、すなわち事前審査のフェーズは、都道府県に提出した申請書類一式について、形式・内容面での詳細な確認が行われるステップです。「仮」という名称から一見軽微な審査と思われがちですが、実質的な内容審査がここで行われるため、書類の完成度が非常に重要です。仮申請の段階で指摘や補正指示を受けることは珍しくなく、その多くは定款の内容、事業計画の数字の整合性、収支予算の妥当性に関するものです。また、仮申請の段階で提出された書類は、原則として本申請において内容の変更ができない点にも注意が必要です。このため、提出直前の“突貫仕上げ”は極めて危険です。スケジュール的には、本申請までに2〜3か月程度のブラッシュアップ期間が設けられることもありますが、書類に対する自治体担当者の修正指示が繰り返されると、結果的に本申請の受付期間に間に合わなくなることも。特に、東京都のように年に2回しか申請受付がない地域では、1回の遅れが半年の遅延につながるため、この仮申請の品質確保がスケジュール管理上の分岐点となります。
- 仮申請では、押印や公証役場での認証は不要
- 書類の体裁、要件充足度を確認され、不備があれば補正指示が入る
- 仮申請から本申請までに内容の変更は不可なため、正確な書類提出が重要
③本申請・審査・認可取得
本申請フェーズは、仮申請を経て内容が固まった申請書類に「正式な証明」を加える工程です。公証役場での定款認証や、役員による実印押印、印鑑証明書の添付といった手続きは、書類の真正性・法的効力を担保するための要件です。この段階では、事業の根幹を支える各種契約の準備も重要となり、不動産の賃貸契約書やリース契約、負債の引継ぎがある場合には、金融機関やリース会社からの「承諾書」が求められます。また、資産を現物出資する場合には、評価証明書や鑑定書が必要になることもあります。これらすべての書類が、都道府県の医療審議会における審査材料となるため、正確さと網羅性が不可欠です。医療審議会では、医療法の要件に加え、経営者の資質や事業計画の実現性、地域医療への貢献性なども問われるケースがあります。自治体によっては、面談や追加説明を求められることもあり、申請者の準備不足が露呈すると認可に時間がかかる場合もあります。この段階は「最終審査」であると同時に、「対外的な信頼性を得るプロセス」でもあるため、資料の整合性や論理構成、説明責任の果たし方が問われます。専門士業と二人三脚で進めることで、確実な認可取得につながります。
- 公証人役場での定款認証
- 役員の実印押印・印鑑証明書添付
- 不動産契約、リース契約、負債引継の承諾書なども必要
- 都道府県による医療審議会での審査後、知事の認可が下りる
④法人設立登記(認可後2週間以内)
設立認可書を受け取ったら、いよいよ法務局での法人登記手続きに入ります。この登記が完了することで、医療法人としての法的実体が正式に成立します。注意すべきは、医療法第46条第1項に基づき、認可書の交付日から2週間以内に登記申請を行わなければならないという点です。万一この期限を超えると、認可が無効とみなされ、再申請の手続きが必要になるおそれがあり、最悪の場合は開業予定日自体が延期となる可能性もあります。登記に必要な書類は、公証役場で認証された定款、設立総会議事録、理事や監事の就任承諾書と印鑑証明、医療法人設立認可書の原本または写しなど、多岐にわたります。特に、役員の氏名、住所、役職などが登記申請書と一致しているかの確認は重要で、形式的な誤記が登記不受理の原因になることもあります。また、登記完了後には「法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)」を取得し、都道府県への登記完了届の提出も必要です。この一連の手続きは、司法書士の専門領域ですが、医療法人独自の書類構成に慣れていないと時間がかかるケースが多いため、医療法人の登記に精通した専門家の協力が不可欠です。法人の“誕生”を確実に成立させる重要な一歩です。
- 登記申請は認可日から2週間以内が法定期限
- 登記完了により、医療法人が法律上成立
- 登記事項証明書(法人謄本)を取得後、登記完了届を都道府県に提出
⑤医療機関の開設許可申請・届出
医療法人として法的に成立していても、医療機関として診療を開始するには、別途「開設許可」または「開設届」の手続きが必要です。これは医療法に基づく制度で、有床診療所や病院では保健所への開設許可申請、無床診療所では開設届の提出を行います。特に有床施設の場合、保健所が現地調査を行い、構造・設備・衛生管理体制が法令基準を満たしているかを厳しくチェックします。ここで問題があれば許可が下りず、予定していた開業日に間に合わなくなることもあります。一方で、無床診療所は比較的簡易な届出手続きで済むものの、開設の10日前までに提出する必要があり、こちらもタイミングを逃すと不備とされるリスクがあります。また、法人として新規開設する場合だけでなく、個人医院からの移行であっても、旧医院の廃止届と新規開設届を同日提出する調整が必要です。これがずれると、保険診療の継続性や患者様への影響が生じるため、非常に重要な工程です。さらに、管理者(院長)の就任承諾書、免許証コピー、施設図面、設備リスト、防火・防災体制の資料など、提出書類も多岐にわたります。経験のない申請者にとっては手続きが煩雑なため、保健所との事前相談を活用し、可能であれば行政書士などの専門家と連携して進めることが成功のカギとなります。
- 有床診療所・病院:保健所への開設許可申請+現地調査
- 無床診療所:診療所開設届の提出(原則10日前まで)
- 施設の図面、医師免許証、管理者承諾書などが必要
⑥保険医療機関指定申請
医療法人としての設立・登記・開設届が完了しても、保険診療を行うためには「保険医療機関」としての指定を受けなければなりません。これは、健康保険法に基づく制度で、厚生労働省の地方支分部局である「地方厚生(支)局」が所管しています。申請を怠ると、開業しても保険診療ができず、自由診療しか提供できない状態になってしまいます。これは診療報酬の収益構造を大きく左右する重大事項です。
指定申請のタイミングは、各地方厚生局ごとに毎月1日または15日を基準日として指定発効するスケジュールが組まれているのが通例です。例えば関東信越厚生局では、毎月1日・15日のいずれかに合わせて申請を行い、所定の審査を経て「保険医療機関指定通知書」が交付されます。この通知書をもって、レセプト(診療報酬請求書)の提出が可能となり、保険診療の報酬請求が正式にスタートします。
必要書類としては、登記事項証明書、開設許可証(または開設届受理書)、管理者の医師免許証写し、施設の図面や設備一覧、管理者就任承諾書、そして保険医療機関指定申請書などが必要です。注意したいのは、法人名義・施設所在地・管理者名などが申請書と登記簿・届出書類と完全に一致しているかです。形式的なミスがあると差し戻しになることも多く、開業日との整合性が取れなくなってしまうことも。
また、既存の個人医院から法人へ移行する場合は、旧医院の保険医療機関指定の「廃止届」も同時に提出する必要があります。この廃止届と新規指定が“同日付”で処理されないと、診療報酬請求に空白が生じ、請求漏れのリスクが発生します。 こうした複雑な手続きを確実に行うためにも、厚生局・保健所・専門士業(行政書士・社労士等)との連携が求められます。
開業日と指定日を一致させ、レセプト請求がスムーズに行えるように準備を重ねることが、健全なスタートの要件です。
- 登記事項証明書
- 開設許可証(または開設届出受理書)
- 医師免許証など
- 通常、申請から1〜2週間で指定通知が発行
- 月初または月中の指定日が設定されることが多い
⑦開設後の諸手続き(税務・社保・医師会など)
「法人登記」や「保険医療機関指定」を終え、晴れて診療をスタートさせたあとも、開設後には多くの実務的な手続きが待っています。 これらを怠ると、税務処理・労務管理・契約実務などでトラブルや遅延が発生し、法人運営に支障をきたすことがあります。
まず、税務関係として**「法人設立届出書」を税務署および都道府県税事務所に提出**します。これは法人が発生したことを正式に税務当局へ届け出るもので、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)、定款の写し、設立趣意書、収支予算書などの添付が必要です。提出期限は設立から2か月以内が原則で、遅延すると青色申告の承認や減価償却費の扱いなどで不利益を被る可能性があります。
さらに、従業員(看護師・事務スタッフなど)を雇用している場合、社会保険(厚生年金・健康保険)の適用手続きを年金事務所で行い、労働保険(労災・雇用保険)の適用届を労働基準監督署・ハローワークに提出する必要があります。これらの手続きは、法人化によって個人事業と条件が異なり、法人としての適用義務が発生するため、早めの対応が求められます。
また、医師会(都道府県・郡市区医師会)への入会も検討が必要です。これは任意ですが、地域医療連携の観点から加入が強く推奨されます。入会には申請書の提出、面談、年会費の納入などが必要で、地域によって手続き内容が若干異なります。加えて、診療報酬の請求業務の委託先(レセプト業者)や医療材料の仕入先、電子カルテ・レセコンの保守業者との契約整備も開設直後に行われるべきです。
銀行口座も法人名義で開設し、診療報酬や各種支払の口座管理を明確にする必要があります。さらに、光熱費・電話契約・水道・ネットなどライフラインの契約も法人名義に変更し、各種契約上の名義ミスがないか確認を行います。看板や封筒・名刺などの印刷物やホームページ情報も法人名に切り替える必要があり、“見た目の整合性”も患者様への安心感に繋がるため、細かい対応が欠かせません。
- 税務署・都道府県税事務所への法人設立届出書
- 年金事務所・労基署・ハローワークへの労務関連届出
- 医師会・歯科医師会・薬剤師会への入会手続き
- 法人名義での口座開設、各種契約名義変更
- 看板・印章・名刺等の法人名称への切替



